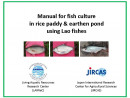ラオス
関連するJIRCASの動き
ラオス教育スポーツ省大臣から感謝状を授与-ラオス国立大学農学部創立50周年記念式典にて
2025年12月9日、ラオス人民民主共和国の首都ビエンチャンで開催されたラオス国立大学農学部創立50周年記念式典において、国際農研の丸井淳一朗主任研究員が、発酵食品分野における長年の国際共同研究の功績に対し、ラオス教育スポーツ省大臣名義の感謝状をラオス国立大学学長より授与されました。
ラオス・イネ換金作物研究所代表団が国際農研を訪問
2025年8月25日、ラオス・イネ換金作物研究所(RCCRC)のシーヴィンケーク・ポンマラット所長をはじめとする4名の代表団が国際農研を訪れ、理事長および理事を表敬しました。
関連する現地の動き
刊行物
Fall Armyworm Proliferation in Mainland Southeast Asia : Government and Maize Farmer Responses
KUSANO, Eiichi, KOBORI, Youichi, JIRCAS Working Report. 93 ( )
広報JIRCAS (14)
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター, 広報JIRCAS. 14 ( )
jircas14-_-.pdf7.66 MB
広報JIRCAS (11)
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター, 広報JIRCAS. 11 ( )
jircas11-_-.pdf4.91 MB
ຄູ່ມືການລ້ຽງປາ ໃນນາເຂົ້າ & ໜອງປາ ນຳໃຊ້ໂດຍຊາວປະມົງລາວ
ສູນຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຊີວິດທາງນໍ້າ (LARReC), ສູນຄົ້ນຄວ້າສາກົນດ້ານກະເສດສາດແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (JIRCAS), マニュアル・ガイドライン. 3 ( )
manual_guideline3-10_-.pdf469.24 KB
Manual for fish culture in rice paddy & earthen pond using Lao fishes
Living Aquatic Resources Research Center (LARReC), Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), マニュアル・ガイドライン. ( )
manual_guideline3-9_-.pdf411.38 KB
関連するイベント・シンポジウム
-
JIRCAS-NAFRI共同研究運営委員会
- 場所
-
ラオス・ビエンチャン市
-
JIRCAS-NAFRI-NUOL共同研究年次会合
- 場所
-
ラオス・ビエンチャン市
-
JIRCAS-NAFRI 共同研究運営委員会
- 場所
-
ラオス,ビエンチャン市
-
JIRCAS-NAFRI-NUOL 共同研究年次会合
- 場所
-
ラオス,ビエンチャン市
出張報告書
| 報告書番号 | 出張年月 | 国名 | 出張目的 | 関連プログラム |
|---|---|---|---|---|
| R07-0389 | 2025年12月 - 2025年12月 | ラオス | 1.ラオスにおける麹甘酒の研究開発に関する成果発表 2.ラオスにおける魚醤のヒスタミン抑制技術の普及促進に関する成果発表 |
食料, 情報 |
| R07-0390 | 2025年12月 - 2025年12月 | ラオス | 1.ラオス大学農学部50周年記念会議における研究成果発表 2.ラオス水稲作の省力化技術の現状と課題に関する調査 |
食料 |
| R07-0356 | 2025年11月 - 2025年11月 | ラオス, ベトナム, タイ | ツマジロクサヨトウ防除に関する情報提供と研究協力の協議 | 食料 |
| R07-0291 | 2025年10月 - 2025年10月 | ラオス | 1.玄米麹甘酒の嗜好性調査 2.ラオス連携機関と調製した淡水魚発酵調味料の品質確認、成分分析に関する現地での技術指導 |
食料, 情報 |
| R07-0322 | 2025年11月 - 2025年11月 | ベトナム, ラオス | キャッサバモザイク病抵抗性品種の作出に向けた技術移転 | 情報 |
研究成果情報
- インドシナ諸国におけるツマジロクサヨトウ推奨防除手法の体系化と費用要件(2024)
インドシナ諸国政府の多くは、ツマジロクサヨトウ防除のため化学農薬に加え、薬剤抵抗性管理や生物的防除を推奨している。一方、飼料用トウモロコシ農家の害虫管理は安価な化学農薬の葉面散布が主流で、その費用は限定的である。よって、化学農薬代替技術は十分低コストであることが求められるが、特に種子処理や天敵昆虫の放飼は導入コストを抑えられる可能性があり、技術開発・普及において注目される。
- イネ科ウロクロア属牧草で初のアジアモンスーン向け品種「イサーン」の育成と品種登録(2024)
「イサーン」は、乾物収量の平均値が1年当たり18.8 t ha-1と既存品種よりも約12%多収であり、強い耐乾性や高い粗タンパク質含量などの優れた飼料特性を有するウロクロア属で初のアジアモンスーン向け品種であり、日本では2021年8月に、タイでは2024年7月に品種登録された。無性生殖による種子生産のため、種子から均一な草地造成が容易で、放牧利用に適し、タイの農家の経営安定化や畜産業発展に寄与する。日本でも地球温暖化の適応策として、南西諸島や九州から関東地方での利用が期待される。
- ラオス山地では植栽密度と立地選択によりチーク成長が倍増する(2021)ラオス山間部では植栽密度のコントロールと植栽する斜面の形状や傾斜の選択によって人工林チークは肥大成長および伸長成長に倍程度の差異を持つことから、適地判定が重要である。凹形緩傾斜面の下部が適地として最も推奨され、密植は避けた方が成長がよい。
- ラオス淡水魚発酵調味料のヒスタミン生成は仕込み時の塩分調整で抑制できる(2020)
ラオス農村世帯で生産・消費される淡水魚発酵調味料には製品ごとに塩分のばらつきがあり、低塩分の製品では高濃度のヒスタミンが生成される傾向がある。魚、塩、米糠の重量比を3:1:1となるよう混ぜ合わせる伝統的な製法に従い、仕込み時の塩分を18%程度に調整することにより、発酵に伴うヒスタミンの生成を抑制できる。
- 汎用小型ドローンから陸稲圃場のイネと雑草を高精度で判別できる(2020)
オブジェクトベース画像解析は、画素値の類似したピクセルの集合を1つのセグメントとし、セグメント単位で分類する高解像度画像に適した手法である。同手法を用いて、陸稲圃場のドローン空撮画像を解析することで、イネ・雑草・土壌を高精度で分類でき、圃場内の雑草の空間分布を迅速に把握することで、除草作業の効率化が期待できる。
- アメリカミズアブ幼⾍はキノボリウオの飼料タンパク質源として有効である(2019)
果実残渣等を用いて簡易に生産できるアメリカミズアブ幼虫をタンパク源として調製した餌は、ラオスの主要な養殖対象魚であるキノボリウオにおけるタンパク質同化効率が従来の魚粉飼料よりも優れ、タンパク質含量が少ない飼料でも高成長が期待できる。
- ラオスの重要な⾷⽤⿂パケオの資源保全に資する⽣態的情報(2019)
ラオスの重要な漁業資源であるパケオ Clupeichthys aesarnensis はニシン科の小魚で、乾物や発酵食品の主要な原料であるが、主な漁場では乱獲による漁獲量の減少が強く懸念されている。本種は周年産卵することから、適切な資源管理を行うには禁漁期ではなく禁漁区の設定が有効である。
- 穂ばらみ期の地上分光計測データから収穫前にコメの収量が予測できる(2018)
穂ばらみ期の水稲群落上で分光計測を行うことで、収穫1カ月前に収量を予測することが可能である。さらに早い生育ステージ(幼穂形成期)でも低い精度で収量を予測できるが、開花後の成熟期に入ると予測は困難になる。収量の推定には、分光データのうち窒素とバイオマスに関連したレッドエッジ(700–760 nm)と近赤外(810–820 nm)の波長が重要である。
- キノボリウオの水田養魚は種苗の低密度放流により無給餌でも成立する(2018)
ラオス山村域では、農民の動物タンパク質摂取不足を改善するために養魚振興が求められている。山村域の小規模農家が実施可能な水田養魚において、在来種であるキノボリウオを用いた場合、養魚種苗の低密度放流により無給餌でも高水準の生産性が見込まれ、さらに給餌することで生産性は向上する。
- 養魚ため池の貯留水を雨季水稲と乾季畑作に利用することで収益増が期待される(2018)
ラオス中部の中山間農村では、養魚用ため池の貯留水の活用により、雨季初期に水が不足する圃場の初期灌漑と乾季には畑作を行うための補給灌漑が可能になる。養魚に必要な最低水量を維持することで、ため池を養魚と灌漑に併用できる。また4月上旬に貯留水を抜く慣行法よりも、乾季畑作の灌漑に合わせて2月に水を抜く方が利益の増加が見込まれる。
論文
2025
-
Takai, Toshiyuki , Saito, Hiroki , Marui, Junichiro , Oo, Aung Zaw , Vilayheuang, Koukham , Phongchanmixay, Sengthong , Asai, Hidetoshi (2025) Detection and characterization of quantitative trait loci for phytic acid in grains toward improved black rice in northern Laos. Frontiers in Sustainable Food Systems, 9 :1620644-. https://doi.org/10.3389/fsufs.2025.1620644
2000889868.8 KB