Pick Up
1309. 経済発展水準とエネルギー消費・肥満の関係
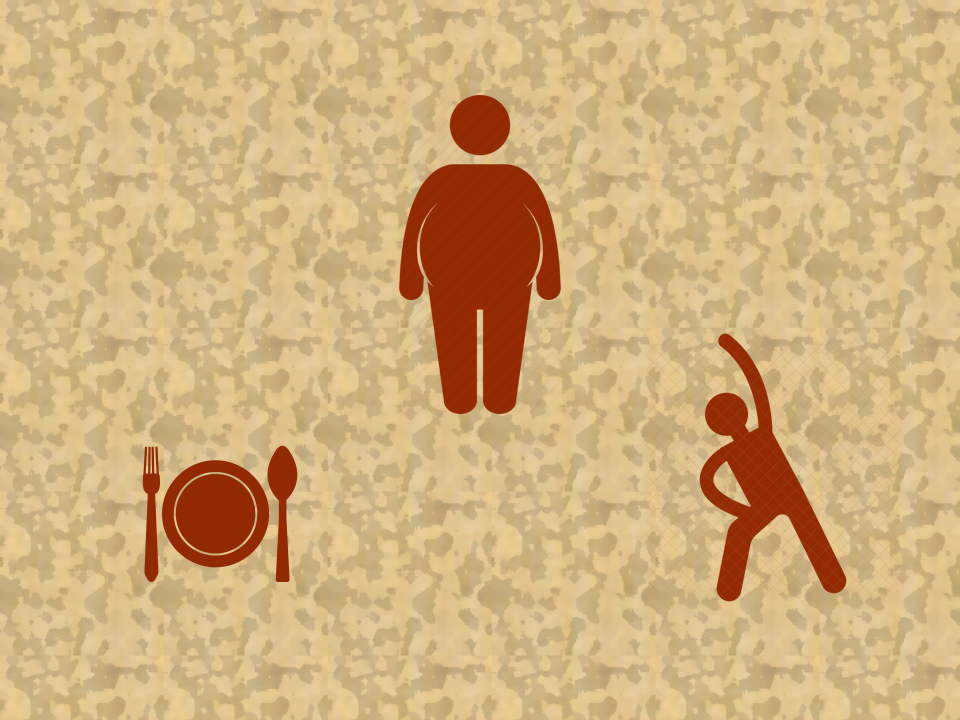
1309. 経済発展水準とエネルギー消費・肥満の関係
世界的な経済発展は、肥満および関連する健康問題の蔓延と関連しています。肥満は世界における死亡率と罹患率の主な原因です。現代の肥満危機の原因は公衆衛生研究において依然として議論の的となっていますが、経済発展に関連しているようです。
例えば、1800年代の米国では肥満は稀であり、今日でも伝統的な農耕・採集社会では依然として稀である一方、過去1世紀の間にほとんどの工業化人口の間では一般的になっています。基本的に、体重増加は消費カロリーよりも多くのカロリーを摂取・吸収することで生じます。公衆衛生機関は通常、この不均衡の原因を身体活動エネルギー消費量の減少と過剰摂取を促進する食生活の変化の両方に帰していますが、消費と摂取の相対的な寄与を評価することは困難であることが判明しています。工業化社会の人口は、伝統的な農業や採集を行うコミュニティに比べて身体活動がはるかに少なく、過去数十年間の経済発展に伴い、工業化社会における日常的な身体活動は減少しています。カロリー摂取量の増加とエネルギー消費量の減少はともに開発に関連した肥満危機の要因として挙げられていますが、それらの相対的な重要性は未だ解明されていません。
PNAS誌で公表された研究では、狩猟採集民、牧畜民、農耕民、工業化社会の住民など、多様な生活様式および経済圏に属する6大陸34集団の成人4,213人を対象に、エネルギー消費量と肥満の2つの指標(体脂肪率およびBMI)を調べました。経済発展は、体重、BMI、体脂肪の増加と正の相関関係にあり、総エネルギー消費量、基礎エネルギー消費量、および活動エネルギー消費量の増加とも相関していました。一方、体格調整後の総エネルギー消費量および基礎エネルギー消費量は、集団間で大きなばらつきがあり、生活様式とは密接には対応していませんでした。体格調整総エネルギー消費量は、肥満度と負の相関を示していましたが、その相関は弱く、経済発展に伴う体脂肪率およびBMIの上昇の約10分の1相当でした。対照的に、推定エネルギー摂取量は経済発展した集団で高く、食事中の超加工食品の割合が体脂肪率と関連していました。これは、経済発展に関連する肥満において、食事摂取量がエネルギー消費量の減少よりもはるかに大きな役割を果たしていることを示唆しています。
結論において、論文は、世界的な肥満危機において食生活が中心的な役割を果たしているからといって、身体活動を促進する取り組みを軽視すべきでないと述べています。日常的な身体活動には、全死亡率および心血管疾患による死亡率の低下からメンタルヘルスの改善まで、幅広く健康上の利点があることが十分に立証されており、健康的なライフスタイルに不可欠な要素です。食事と身体活動は、互いに置き換え可能なものではなく、不可欠かつ補完的なものとして捉えるべきです。
本研究の結果は、先進国における食品を肥満誘発性にする要因を特定する必要性を浮き彫りにしました。一方で、経済発展と近代的食料システムの導入の影響がすべて否定的なものというわけではありません。現在の世界的な生産・供給ネットワークにより、地球上のほぼすべての人々が手頃な価格の食品および食品成分を利用できることが保証されています 。肥満を追跡し予防する取り組みは、BMIではなく体脂肪の指標を使用し、支出ではなく食事摂取量に焦点を当てることで改善されます。 栄養価の低い肥満を引き起こす食事を促進せずにカロリー利用可能量の増加のメリットを最大化するために食品環境を規制することは、公衆衛生における重要な課題であり、世界的な経済発展が続くにつれて、この課題はより深刻化するでしょう。
(参考文献)
Amanda McGrosky, et al. Energy expenditure and obesity across the economic spectrum, PNAS.
July 14, 2025. 122 (29) e2420902122. https://doi.org/10.1073/pnas.2420902122
Catherine Offord, New study blames diet, not physical inactivity, for obesity crisis, Science. doi: 10.1126/science.z9i2b0l
(文責:情報プログラム 飯山みゆき)
