Pick Up
1339.気温上昇と糖分消費量の関係
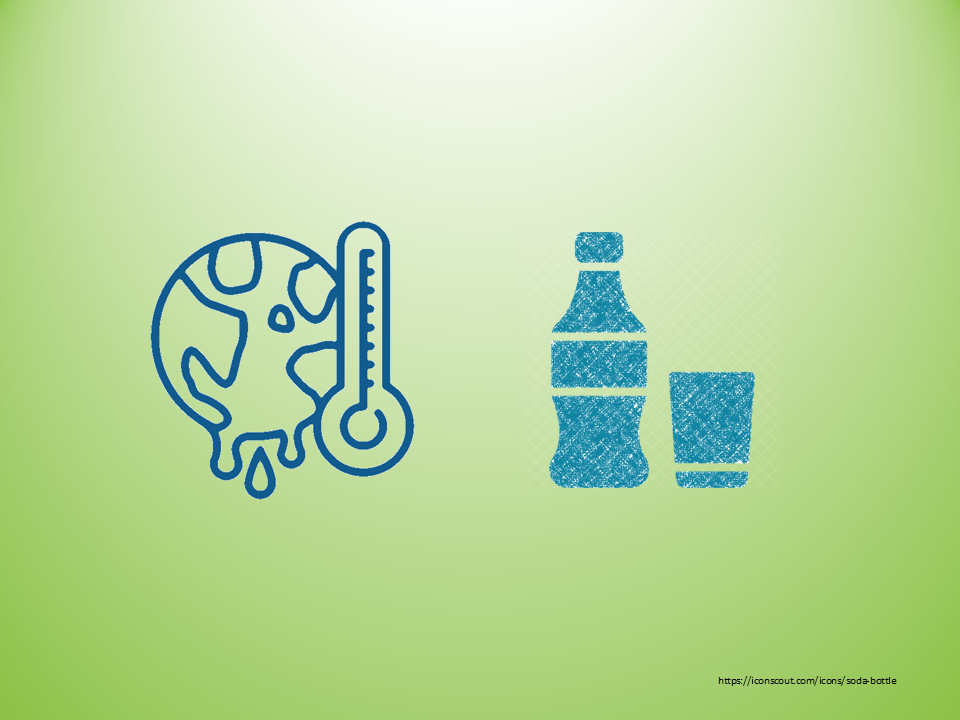
1339. 気温上昇と糖分消費量の関係
気候は、複数の経路を通じて食料消費と栄養に影響を与えます。気温や降水パターンの変化は、農作物の収穫量、農作物の栄養含有量、水産物の豊かさと流通、家畜の健康と生産性に影響を与え、これらは食料価格、栄養価、栄養関連疾患にも影響を及ぼします。異常気象は輸送・流通網を混乱させ、食料安全保障を脅かす可能性がある一方、二酸化炭素濃度の変化などの気候関連要因は、農作物の栄養価を低下させる可能性があります。
このように、供給側に関する文献は多数存在するものの、気候が食生活の需要にどのように影響するかを評価した研究はほとんどありません。猛暑は、代謝の亢進によって水分損失を増加させるため、水分補給の必要性を高め、冷凍飲料やデザートなどの冷たい食品の消費を促す傾向があります。気候変動は、特に糖分を多く含む食品や飲料の消費に慣れている国や地域において、過剰な添加糖の摂取を悪化させ、肥満、さまざまな代謝障害、心血管疾患、がん、その他の健康上の合併症のリスクを大幅に増加させることを通じ、深刻な健康被害をもたらす可能性があります。しかし、こうした影響はほとんど定量化されてきませんでした。
Nature Climate Change誌で発表された研究は、2004年から2019年までの米国における世帯レベルの食品購入データを用いて、添加糖の消費量が気温と正の相関関係にあることを明らかにしました。特に12~30℃の範囲においては、主に砂糖入り飲料や冷凍デザートの消費量増加を通じて、添加糖の消費量が1℃当たり0.70gの割合で増加しました。加糖飲料が主な牽引役として浮上し、12℃から30℃の間で消費量が急増(添加糖、0.73 g/℃)する一方、冷凍デザートの消費量の増加ははるかに緩やか(0.06 g/℃)で、ベーカリー製品・油脂・粗糖由来の糖分はわずかに減少しており、冷蔵された水分補給食品への代替が進んでいる可能性を示唆しています。
気温上昇に応じた添加糖の消費増影響の程度は、所得や教育水準の低い世帯でより大きくなり、脆弱な層はさらに高いリスクにさらされると予測されています。社会経済的地位の高いグループが天候の変化にあまり反応しないのは、特に職場におけるミクロ環境の気温差に起因している可能性があります。所得や教育水準の高いグループは、健康への懸念からより健康的な食品や飲料を選択する可能性があり、これは添加糖の消費量が少ないことに反映されています。これらのグループは暑い天候での製品プロモーションへの反応が低く、水分補給のために低糖飲料を選択することにつながっていると考えられますが、これら飲料も遊離糖分を含んでいるため必ずしも健康的ではありません。
研究結果は、添加糖の過剰摂取による健康リスクを軽減し、気候変動への食生活の適応を探ることが極めて重要であることを浮き彫りにしました。
(参考文献)
He, P., Xu, Z., Chan, D. et al. Rising temperatures increase added sugar intake disproportionately in disadvantaged groups in the USA. Nat. Clim. Chang. 15, 963–970 (2025). https://doi.org/10.1038/s41558-025-02398-8
(文責:情報プログラム 飯山みゆき)
