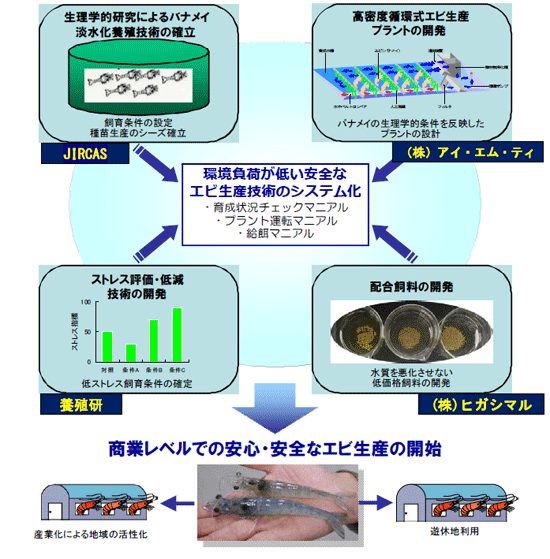安全な国産エビ(バナメイ)の生産技術のシステム化
エビの育成に必要な生物学的な基礎的知見を背景として、システム工学の知見を融合させ飼育試験を行い、徹底したコスト意識で実験から実証段階までの一貫した生産開発をする(2008年9月より)。同プラントは薬剤を使わない安全・安心なエビを供給する。
背景・ねらい
海産エビ養殖業は100億ドル以上の生産額で、世界規模の巨大水産食品産業に成長した。一方で、集約的なエビ養殖が環境問題(残餌や排泄物による海洋汚染)を引き起こすことから、環境への影響が少ない実用レベルの養殖エビ生産技術開発が求められている。年間生産量300万トンにのぼる海産エビの75%はアジアの発展途上地域が担っている。その需要は、米国、日本のみならずヨーロッパ、中国でも年々伸びている。中南米原産のバナメイは美味で、低脂肪の健康的な食品としても注目されている。成長が早く病気に強いことから、東南アジアでもバナメイの養殖場が爆発的に増えている。バナメイは低塩分水でも飼育できることから環境負荷が低く、安心、安全な閉鎖循環式飼育技術を養殖産業にまで発展させる生産システムを開発する。
成果の内容・特徴
- エビの育成に必要な基礎データ(浸透圧調整、酸素要求量、アンモニア排出量、水温、流速等)を定量的に把握する。
- 成熟制御技術および熟度判定法等の研究成果と機械工学の知見を融合させ、世界初の「屋内型エビ生産システム(ISPS)」を開発した。安心、安全なエビ生産の実証プラントを新潟県妙高市に建設する。
- エビのストレス評価方法を開発し、高密度状態でも低密度状態と同じように育成できる。
- 給餌効率および餌養効果の高く、水中保型性に優れ、閉鎖循環式に適した安価な餌を開発する。
- (独)国際農林水産業研究センター、(株)アイ・エム・ティー、(独)水産総合研究センター養殖研究所および(株)ヒガシマルが共同でプラント開発に取り組み、その成果により第7回産学官連携功労者表彰(農林水産大臣賞)を受賞した。
成果の活用面・留意点
- 未経験者でも従事できるように各種マニュアル類を整備し、現地での教育に利用している。
- エビ育成マニュアルを作成し、実証プラントで育成実験を行い、平成19年9月より商業運転を、平成19年12月より妙高ゆきエビ(10尾入×2袋、2100円)として販売を開始した。
- 内陸部の遊休地を有効利用できるため、「立地条件を問わない」、「地産地消をベースとした地域産業の活性化」が期待できる。
- 第1号プラントで生産されたバナメイは、中小企業地域資源活用促進法に基づく新潟地域産品に指定された(2008年)。
- 得られたエビの各種生物学的な基礎知見は開発途上地域の養殖技術向上に寄与する。
具体的データ
- Affiliation
-
国際農研 水産領域
- 分類
-
技術A
- 予算区分
- 受託 [生研センター] 交付金[エビ成熟]
- 研究課題
-
安全なエビ(バナメイ)の生産システム・プラントの開発
- 研究期間
-
2008年度(2004~2008年度・2006~2010年度)
- 研究担当者
-
ワイルダー マーシー ( 水産領域 )
ORCID ID0000-0003-2114-2000科研費研究者番号: 70360394奥津 智之 ( 水産領域 )
科研費研究者番号: 40456322姜 奉廷 ( 水産領域 )
ORCID ID0009-0004-9970-6923科研費研究者番号: 00649022JASMANI Safia ( 水産領域 )
JAYASANKAR Vidya ( 水産領域 )
奥村 卓二 ( 養殖研究所 )
三上 恒生 ( 株式会社アイエムティー )
野原 節雄 ( 株式会社アイエムティー )
野村 武史 ( 株式会社アイエムティー )
福﨑 竜生 ( 株式会社ヒガシマル )
慶田 幸一 ( 株式会社ヒガシマル )
- ほか
- 発表論文等
-
Jasmani et al. (2010) Fisheries Science. 76(2): 219-225.
松田ら (2010) 日本水産学会誌, 76:210-212.
Jayasankar et al. (2009) Japan Agricultural Research Quarterly (JARQ), 43: 345-350.
- 日本語PDF
-
2009_seikajouhou_A4_ja_Part2.pdf278.42 KB